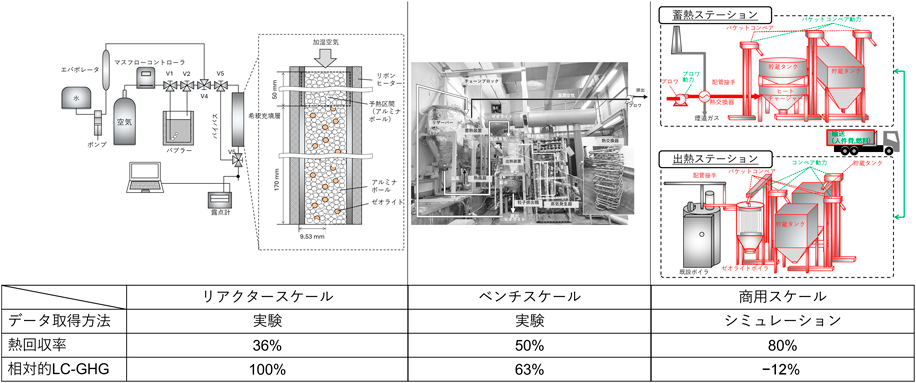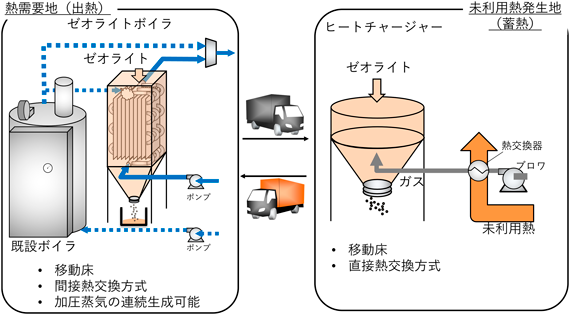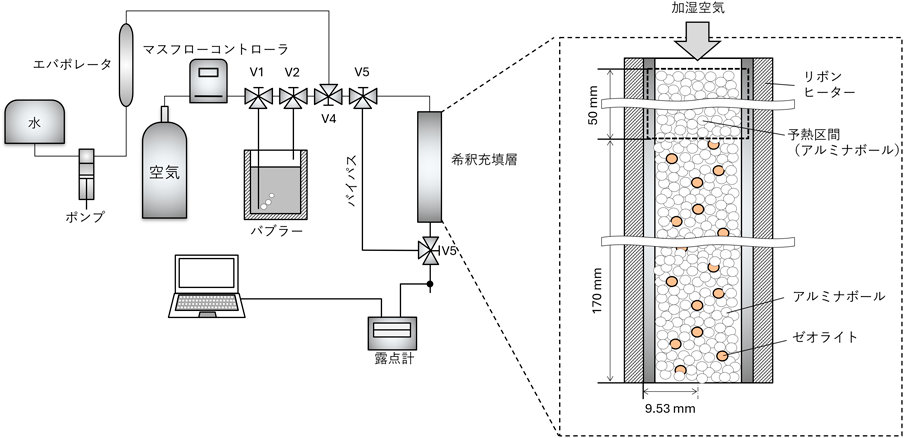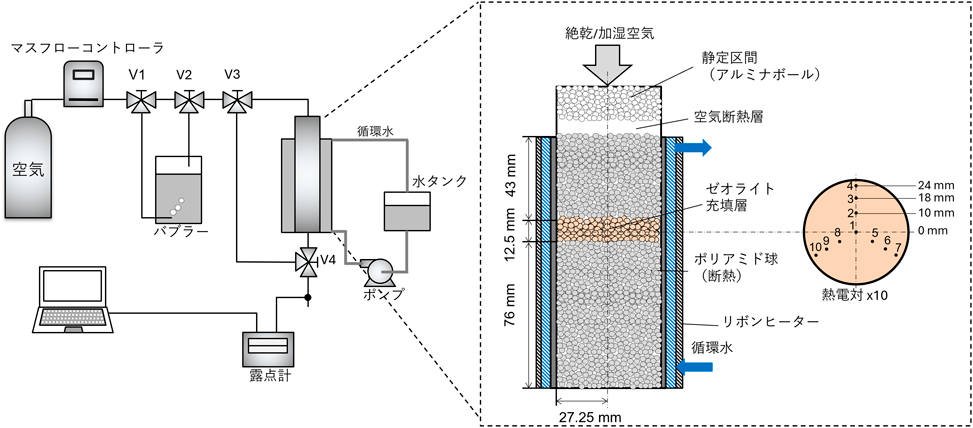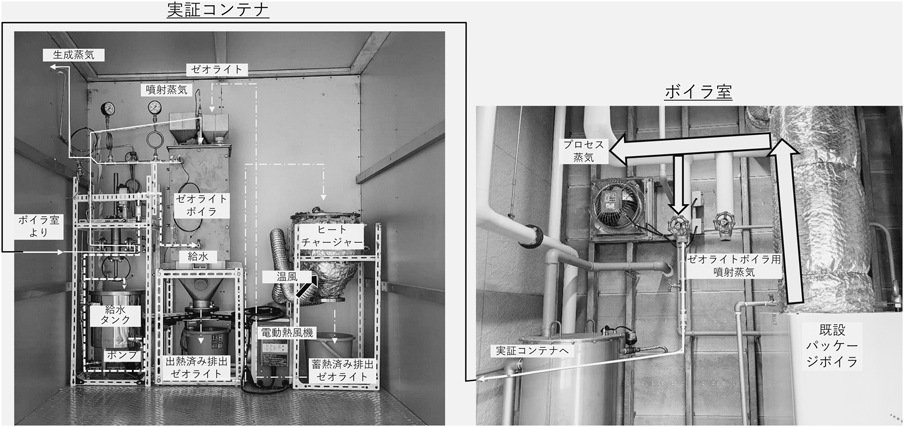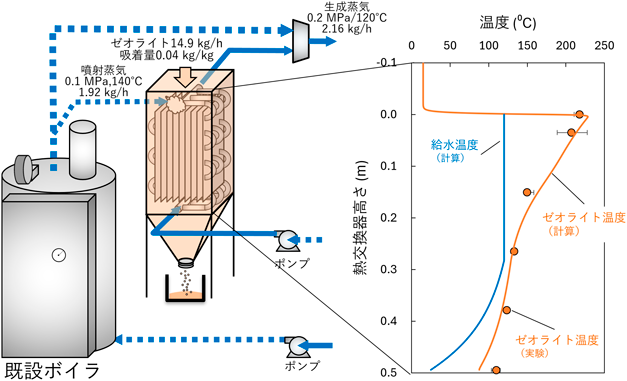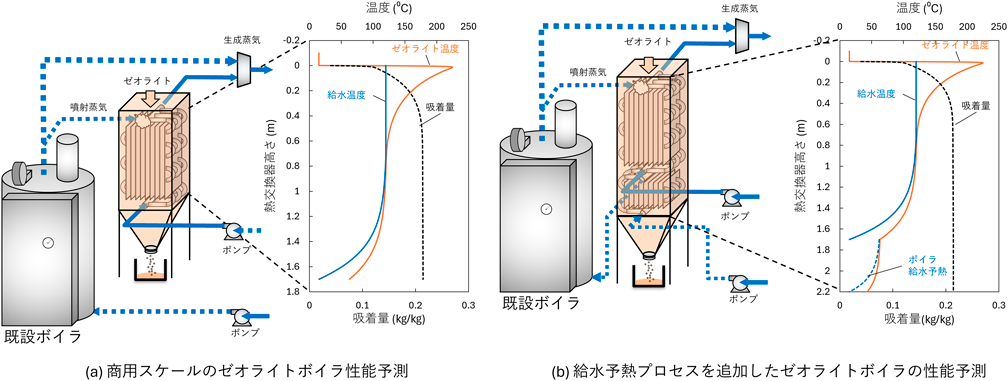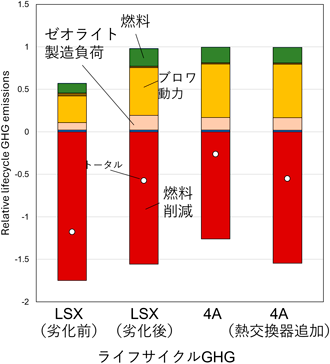ライフサイクル思考からみたゼオライト系蓄熱システムの材料選択の検討Material Selection for Zeolite for Thermal Energy Storage System from Life Cycle Thinking
1 東京大学未来ビジョン研究センターInstitute for Future Initiatives, The University of Tokyo ◇ 〒113–8654 東京都文京区本郷7–3–1
2 東京大学工学系研究科化学システム工学専攻Department of Chemical System Engineering, The University of Tokyo ◇ 〒113–8656 東京都文京区本郷7–3–1